家具は「モノ」ではなく「文化」である
家具というのは、単なる「モノ」として消費されるものではありません。人々はそこに文化を感じ、あるいは憧れを抱いて家具を選びます。
インテリアにはテーマがあり、そのテーマは文化的背景によって生まれます。
つまり家具は「文化」によって価値づけられているのです。
しかし、最近はこの「文化としての家具」の重要性が見過ごされつつあります。この軽視こそが、衰退していく最大の原因となるかもしれません。
文化は「関わる人の多さ」で育つ
文化というのは、モノの良し悪しだけで成り立つものではありません。
そこに関わる人の数、つまり「コミュニティの広がり」があって初めて文化として成立します。
かつて、ある有名スポーツブランドは強力な文化の象徴でした。
しかし近年、既存の小売パートナーを軽視し、自社直販中心の戦略に大きく舵を切りました。その結果、売り上げは低下し、ブランドの地位も揺らいでいます。
パートナーを切れば、それに関わる人も減ります。
つまり文化を支えるプレイヤーが減少するのです。
どれだけSNSやデジタルマーケティングに注力しても、実際に「街で使っている人」「紹介する人」「売っている人」がいなくなれば、リアルな文化の温度感は消えていきます。
さらに、代わりにライバルの販売が進めば、自らの立ち位置さえ失いかねません。
コピーが台頭する
物量で負けると、インターネットの検索もSNSもコピーであふれるようになります。
宣伝費はコピー市場の方が多く支払われるため、正規品よりコピーの方が強い市場になります。
単純にコピー市場の方が売り上げ規模が大きく、またインフルエンサーに支払われるインセンティブも高額です。
私自身も経験がありますが、コピー市場の依頼条件は格段に良いです。(依頼は受けませんでした)
ファンがいなくなり、お金だけで繋がるネットワークでは文化の再生は起こりません。
必然的にそうなっていくのです。
「安売り」が文化を壊す
もう一つの問題は、ブランド価値を下げる安売り戦略です。
短期的な売上や在庫処分を目的に安易に値引きを繰り返すと、消費者はそのブランドに「高い価値」や「文化的な憧れ」を感じなくなっていきます。
家具業界でもよくある話ですが、「安く手に入る」ことが当たり前になれば、やがてそのブランドは「安いから選ばれるだけ」の存在に変わってしまいます。価格でしか競争できない世界に突入すると、文化は簡単に崩壊します。
そもそもセールをするということは、自らを無能だと宣伝しているようなものです。
もう新しい有用な製品も作れず、価値を作ることもできませんと広告しているようなものです。
そんなものを求める人は居ません。
また中古価格は正規価格の下支えになります。
セールによって中古市場の値付けが下がり、また、玉数も増えることで一気に価値が暴落します。
このインフレ・物価高時代に安売りをしないと売れないようなものは市場も消費者も価値がないと判断します。
消費者が求めているのは価値が下がらず上がり続けるものです。
高級ブランドの勢いが鈍る理由
一方で、高級ブランドも今大きな壁に直面しています。彼らは決して安売りはしません。
それでも(一部を除き)ブランドの勢いが鈍り始めているのです。
それは「文化的憧れ」や「象徴的な意味合い」が薄れてきているからです。
かつては「それを持つこと」がステータスであり、語れる物語がありました。
ところが現在は、誰もが持つ時代になり、希少性や象徴性が薄れたことで、所有する意味が失われつつあります。
さらに、ブランド側もマーケティング偏重になり、「ストーリー」や「文化的な文脈」よりも「商品をどう売るか」ばかりを追いかけている印象が強まっています。
これでは「文化」ではなく、単なる「ビジネス」でしかありません。
メーカーやデザイナーの中には、自分たちに価値があるから売れるのだと勘違いしている者もいます。
しかし実際には、彼らは文化を作り上げるプロセスの中で「選ばれ、担ぎ上げられた」存在に過ぎません。
つまり、勝手に見つけられて文化に組み込まれたにすぎないのです。
神輿から降りれば価値は失われます。
神輿から降りたのは、「自分たちに価値があり力がある」「自分こそがルールだ」と傲慢に振る舞っても売れると錯覚したからに他なりません。
安売りで価値を失う存在もあれば、文化の語りを失って価値を失う存在もある。
どちらも本質的には「文化の断絶」による衰退だと言えるでしょう。
アジア製品の台頭と欧米ブランドの迷走
今、アジア製品の品質は目を見張るほど高くなっています。消費者は「製造元から直接、高品質なものを買いたい」と考えるようになりました。
一方で欧米ブランドは、「品質向上」や「革新的な製品開発」から目を背け、デザイナーやブランドストーリーばかりを前面に出す傾向にあります。「これは私のデザインだから価値がある。黙って買え」という姿勢が透けて見えるのです。
しかし、それは現代の消費者には通用しません。
文化が断絶した存在には、もう誰も心を動かされない。それが現実です。
家具の文化は、一度途絶えると戻らない
特に家具は、一度文化が断絶すると取り返しがつかなくなります。
家具には歴史があり、修理・メンテナンス・継承といった文化的知識を持つ人々が支えてきました。
知識の習得には膨大な時間を要します。
数十年、数百年の歴史を知識として理解するには歴史研究家のように長い時間と経験が必要です。
しかし今、それを伝える人がほとんどいなくなりつつあります。
この状態で文化が失われれば、それはもう「終わり」を意味します。
インフルエンサーによる宣伝とビジネスの変質
インフルエンサーは根本的に資金によって繋がっている人たちです。
宣伝をするのも自分にメリットがあるから、お金がもらえるからです。
つまり裏を返せば、他が資金提供をすれば他社でも宣伝しますし、より良い条件で宣伝するのです。
ファンは違いました。
なぜなら自分に利益が無くたって買いますし、使いますし、宣伝しました。
それが自然発生的に広がったのは、現場で支える人たちがいたからです。ファンは共有したいのです。
それがSNSになり、SNSは「シェアが伸びる者だけ紹介すればよい」という世界になりました。そしてお金がもらえるかどうかが基準になってきています。
このインフルエンサービジネスに関しては、アジアの企業が圧倒的に優勢です。
欧米の企業は太刀打ちできないほどの資金力を持ち、非常に狡猾です。だから勝ち目はありません。私自身にも案件が来ますが、条件が驚くほど良いです。
そもそも以前は、各界のクリエイターが自発的に選んでおり、その情報が公開されたことで憧れが生まれました。お部屋紹介や仕事場紹介などがその代表例です。
それが今は、お金を払って、あるいは無償で提供してインフルエンサーに紹介させる。
何も作らず、文化を作らず、社会を維持する仕事でもないインフルエンサーにお金を払って宣伝してもらうなど、どちらが正しいかは明白です。
「文化を理解しない職業社長」という病
そしてもう一つ、見逃してはならないのが、文化の意義を理解せずに経営の舵を握っている“職業社長”たちの存在です。
彼らはの目に映るのは自身の評価だけ。
文化も歴史も、ユーザーが何を愛してきたかも見ようとしません。
「今期の数字をどう作るか」「株主の顔色をどううかがうか」そればかりを考え、ブランドが長年積み上げてきた文化や象徴性の価値を、自らの手で破壊してしまうのです。
短期的な利益を優先し、
- 安売りを決断し
- 販路を切り捨て
- 関係者を排除し
- 文化を支えてきた人々の熱量を断ち切る
また売り上げを拡大することが自身の実績になるため短絡的に買収を繰り返します。
売り上げ規模を大きくする──その結果、ブランドの魂そのものが消えていく。
しかし彼らには、その「見えない損失」が見えません。
数字に出るのは先ですし、どうせ辞めても次の会社に行くだけです。
短期的な報酬を目的に点々としているだけです。
このような経営者がブランドの文化にトドメを刺し、業界の土壌を痩せ細らせていく現実を、私たちはもっと直視するべきです。
まとめ:文化のない業界に未来はない
家具を含め、あらゆるものには「文化」と「憧れ」が必要です。
この視点を持たず、ただ「売れればいい」というスタンスを取り続ければ、やがてその業界には人が集まらなくなり、文化は静かに消えていきます。
そして一度消えた文化は、もう二度と戻りません。一度離れた人はもう戻らず、過去の人たちのようにその分野を追求してくれるような人たちは今後現れないでしょう。
結論はこれです。
つまり、終わった文化は復活することはありません。
こうして過去のものになっていくのです。
異なる文化が主流になった時に気づきます。
そこには居場所が無いことに。


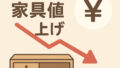
コメント